反カルト弁護士とディプログラマーの協力関係を無視して、日本の統一教会問題を理解することはできない。
Bitter Winterによる書評
全5本の記事の2本目 1本目の記事を読む
Read the original article in English.
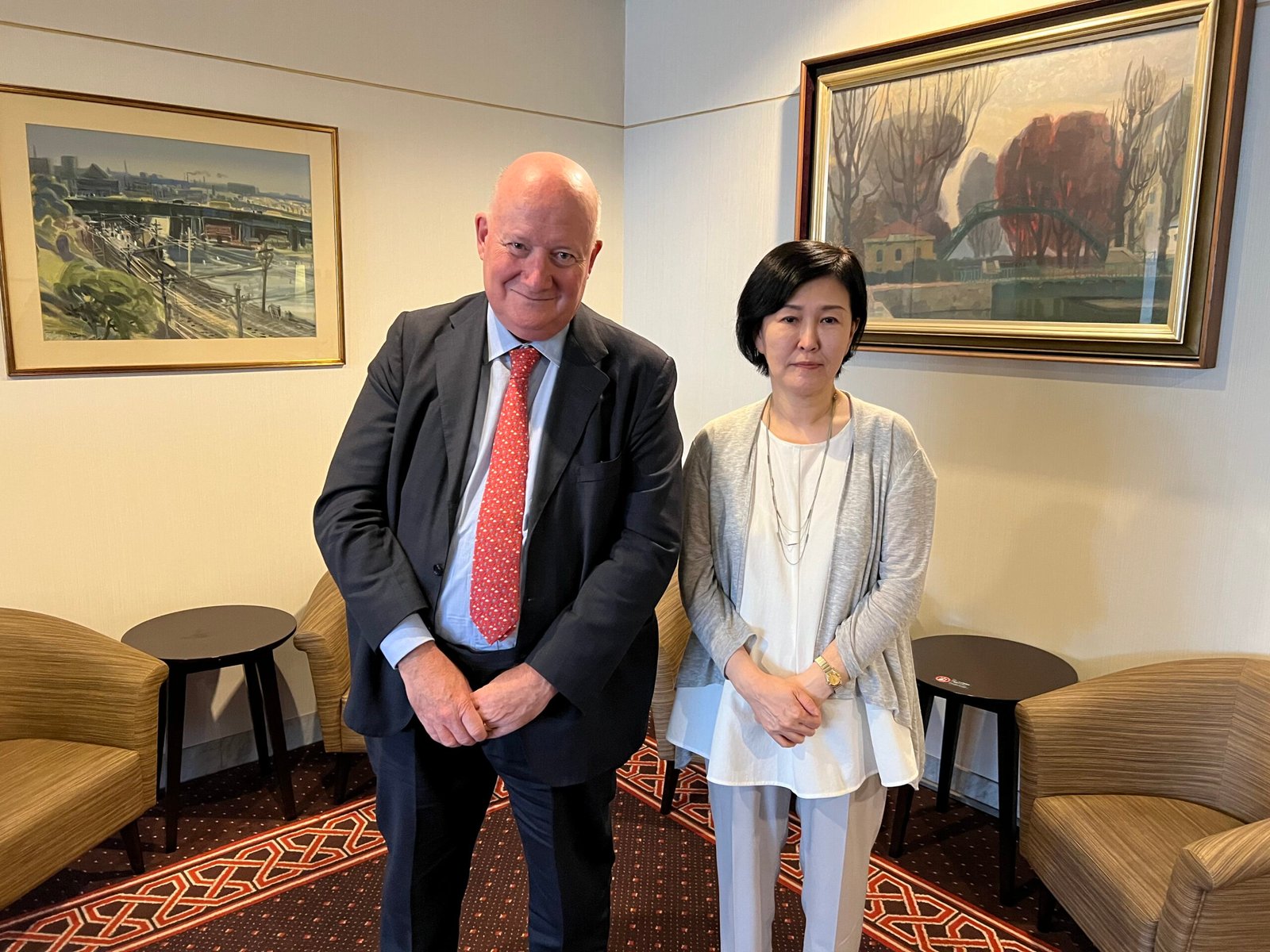
本連載では、ジャーナリストで社会学の専門家である福田ますみ氏による、日本のベストセラー『国家の生贄』を読み解いていく。本書はすでに、山上徹也被告の裁判や、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐる日本社会の認識に、大きな変化をもたらしている。この回で福田氏は、過去数十年にわたり世論を形成してきた一つの組織に焦点を当てる。それが、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)である。
第2章では、福田氏はこの全国弁連とはいったい何者であり、35年にわたって何をしてきたのかを問いかける。本章はきわめて率直な疑問から始まる――全国弁連は、本当に消費者保護団体なのか。同団体は被害者救済を掲げ、旧統一教会によって被害を受けたとされる人々のための法的な受け皿と自らを位置付けてきた。福田氏はその実像を一つ一つ検証していく。
福田氏が指摘するのは、2009年の時点で、旧統一教会がかつて「霊感商法」(霊的な意味を付与した物品を高価な値段で売りつける商法)と呼ばれた資金集めを、すでに停止していたという事実である。
当然被害件数が減少すれば全国弁連はそれを喜ぶはずだが、彼らはそれを歓迎せず、“官僚のパニック”のような反応を見せた。自分たちの存在意義である被害件数が減少すると、多額の献金まで「被害」に含めるなど、むしろ統計を水増ししたのである。その論理はシンプルだった――被害件数が減少するなら、「被害者」の定義を拡大しなければならない。

福田氏はさらに見過ごすことのできない傾向を指摘する。メディアで霊感商法の被害者として紹介されてきた多くの「元信者」は、一般的な元信者ではなかった。彼らの多くは、拉致監禁され、信仰を放棄するよう強要された人々だったのである。教団を離れたのは自由意思によるものではなく、強制だった。
では、こうした「被害者」を、いったい誰がメディアに提供していたのか。福田氏によれば、その役割を担っていたのは、日本における強制棄教の歴史の中核をなす脱会屋・宮村峻氏であった。雑誌やテレビから「カルト被害者」への取材を求められれば、自身が脱会させた元信者を送り出していたのである。
安倍元首相の暗殺後、こうした証言に関するメディアの要請は急激に高まった。福田氏が指摘するように、その時期に大きく取り上げられた声のほぼすべては、拉致監禁され、信仰を放棄するよう圧力をかけられた人々の証言だった。
外部の視点に立てば、全国弁連の主眼は必ずしも消費者保護にあったわけではないことが分かる。その根底にある使命は、政治的・思想的な対立に深く根ざしたものだった。この点を理解するため、福田氏は歴史を遡る。旧統一教会は1959年に日本に進出し、1960年代後半には反共産主義運動の中核を担う組織として、国際勝共連合を設立した。一方、全国弁連は左派的思想に深く根ざしていて、反共運動に長年反対し、スパイ防止法の制定にも抵抗してきた。
このように捉えると、全国弁連の活動はまったく異なる意味を帯びてくる。旧統一教会が宗教法人として認可された直後から、左派系の活動家の間では、すでにその法人格を取り消すべきだという声が上がっていた。福田氏は、教団が“正体隠し”と非難されてきた一方で、全国弁連もまた、30年以上にわたって自らの政治的動機を隠し続けてきたと示唆する。言い換えれば、相手の策謀を非難してきた組織が、実は長年にわたり、自らがそれを実践してきたというのである。
第2章で思想的な枠組みを明らかにしたとすれば、第3章では、日本における強制棄教システムを実際に動かしてきた力、いわゆる舞台裏の人物が登場する。プロの脱会屋・宮村峻氏である。福田氏は、拉致監禁に関する数々の証言の中に繰り返し現れる宮村氏の姿を、読む者の背筋が凍るほど鮮明に描きだす。

拉致監禁を取り仕切る中心人物でありながら、宮村氏はこれまで一度も刑事責任を問われてこなかった。彼の戦略は、そのすべての責任を信者の親に転嫁することだった。福田氏は、彼こそが、この一連の仕組みを主導した人物であることを明らかにする。成人した子どもをどのように拉致するかを家族に助言し、監禁を監督し、最終的に彼らを「解放」するための証として民事訴訟を起こすよう被害者に圧力をかけた。
福田氏は、宮村氏をこの「無限ループ」を作り出した人物と表現する――拉致監禁、強制棄教、訴訟、メディアでの証言、そして新たな拉致監禁の正当化。このように、無限に続くサイクルが作り出されていたのである。
さらに福田氏は、被害者の証言を手がかりに、宮村氏の内面にも踏み込む。複雑な家庭環境で育った彼は、自身の心の傷を、信者たちに重ね合わせていたのではないか。彼は、信者が信じる「父母の愛」を欺瞞とし、信者を脱会させる過程そのものが自分の傷を癒す方法となっていたと推測する。
宮村氏の長期的目標は、旧統一教会の資産を枯渇させ、最終的には解散に追い込むことにあったと福田氏は指摘する。それは偶発的な結果ではなく、当初から一貫していた。
しかし、こうした宮村氏の活動は長年黙認されてきた。福田氏は、彼の活動を可能にしてきた社会的制度に目を向け、その中でも、メディアにその責任を厳しく問う。「報道しない自由」により、ジャーナリストはディプログラミングに社会的正当性を与えた。拉致監禁という過酷な現実は、報道から一切無視され、その結果ほとんど検証されることのないまま、何十年にもわたって存続することになったのである。

その結果は、司法と倫理の深刻な歪みであった。家庭連合の信者たちは、日本国憲法や国際人権規範の埒外に置かれてきた。
警察も、「親族間の問題」として介入を避け、法の下の平等は事実上否定された。
福田氏が下す結論は重い。本来、市民を守るべき制度が、むしろ彼らを見捨て、「救済」の名の下に行われた犯罪に、何千人もの人々を無防備なままさらしてきたのである。



