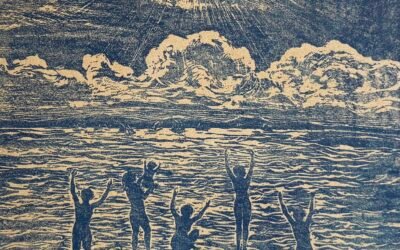日本弁護士連合会は、悪評高いフランス反カルト政府機関の日本版クローンをつくろうとしている。
パトリシア・デュバル
全2本の記事の2本目(1本目の記事を読む)
Read the original article in English.

マインド・コントロールを犯罪化するという1つ目の提言に加え、日本弁護士連合会(以下「日弁連」)が2025年2月25日に国会へ提出した2つ目の提言は、2023年11月15日に行った「カルト問題に対して継続的に取り組む組織等を創設することを求める提言」に基づくものだった。
日弁連は、政府に対し、主管省庁の下に省庁横断的な常設対応組織を創設し、以下の取組みを行うよう求めている。
- 集積された情報に基づく分析
- カルト被害に関する注意喚起及び広報
- カルト問題に取り組む民間団体との協業および民間団体への財政支援
この提言は、フランスの「セクト的逸脱行為関係省庁警戒対策本部(MIVILUDES)」をそっくりコピーしたものである。
しかし、MIVILUDESの実態はというと、「集積された情報」とされるものは、宗教的少数派を「カルト」と呼び軽蔑視する親族や知人から寄せられた、一方的な告発や非難に基づいており、当事者である団体がこうした情報に反論する機会は全く与えられていない。
MIVILUDESは、フランスの裁判所からこれまで、こうした報告を「集積された情報」として年次報告書に掲載し、さまざまな少数派を中傷したとして、何度も非難されてきた。
また、「注意喚起及び広報」と称する取り組みも、実際にはMIVILUDESのこうした団体へのレッテル貼りキャンペーンであり、その多くは国から資金提供を受けた民間の反カルト組織を通じて実施される。
宗教または信条の自由に関する国連特別報告者は、フランスに関する2006年の報告書(本記事の1本目で引用)において、これらすべてを非難している:
「108. しかし報告者は、フランス当局が採用した政策や措置によって、これらの団体の構成員の宗教または信条の自由の権利が不当に制限される状況が引き起こされているとの見解を示している。さらに、これらの団体の一部を公に非難し、その構成員にスティグマを付与することは、特にその子どもたちに対して、特定の形態の差別をもたらしている。」フォームの始まり
そして特別報告者は、フランス政府に対し次のような勧告を行った。
「113. さらに報告者は、民間の取り組みや政府が支援する団体によって国内各地で実施されている対策活動やキャンペーン、とりわけ学校制度内で行われているものについて、これらの団体の子どもたちが悪影響を受けることを避けるために、政府がより注意深く監視することを勧告している。」
しかし、こうした勧告とは正反対に、日弁連は国会に対し、旧統一教会の二世信者に関するさらなる提言を行った。
同じくマインド・コントロール理論に基づき、信者の子どもの「脱会」に関する提言が国会に提出されたのである。
この提言は、日弁連が2023年12月14日に発表した「宗教等二世の被害の防止と支援の在り方に関する意見書」に基づいていた。
同意見書では、「出生時または幼少期から信仰を強制される宗教二世の問題」や、彼らが「親の宗教的信念によって精神的・経済的虐待(恐怖や罪悪感の植え付け、宣教活動の強制など)」を受けるとされる状況が取り上げられている。

この提言は、宗教教育は親によって子どもに押し付けられており、子ども自身が自由に選んだものではないため、これに対抗すべきという仮定から生じている。
しかしこれは、日本が署名した条約で保障されている、「父母が、自己の信念に従って児童の宗教教育を確保する自由を有する」ことに明白に反するものである。(自由権規約第18条4項、児童の権利に関する条約第14条2項)
日弁連は、「子どもの意見は、乳幼児期からの保護者の宗教的価値観に強く影響を受けている」と認識した上で、「子どもが明確な意見を表明できない場合も、子どもの権利保障に遺漏がないよう対応する必要がある」としている。
特に、「子どもは、信仰心を育むに当たって監護者である親の影響を強く受けている上に、与えられた信仰を批判的に検討する能力が十分ではない場合もある」という。このような理由から、日本の国公立学校では、子どもに対し親の信仰について「批判的思考」を育てることを目的とした「啓発活動」や、「人権教室」と称して旧統一教会への非難や、その信者を犯罪者のように描く授業が行われている。フォームの終わり
この意見書では、学校教育現場や相談機関において、ガイドライン(「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」)(日本語リンク)を広く活用することを推奨している。このガイドラインについては、2024年4月に4名の国連特別報告者によって日本政府に公式書簡が送られ、その中で、国際人権基準およびそれに対する日本の義務に反するものであると指摘されている。
このガイドラインには、例えば、子どもを宗教活動に参加させることは「心理的虐待」にあたること、幼少期から言葉による叱責や「地獄」への言及などによって恐怖を刷り込むことは児童虐待に該当する、などが含まれている。
日弁連はこの意見書の中でさらに踏み込み、宗教法人による子どもへの宗教教育を法律で禁止し、その違反を法人解散の事由とすることを推奨している。
日弁連はその理由として、「子どもは、与えられた信仰を批判的に検討する能力が十分ではない」、「子どもには適切な教育が必要」、「子どもが自由な信仰心を育みながら健全な成長・発達を遂げることを保障するために、宗教活動への参加を執拗に指示・慫慂したり、日常生活における活動を規律することに対して、一定の制限を加えることにも合理性がある」と結論づけている。
それゆえに、日弁連は宗教法人法を改正し、「宗教法人に対し、子どもの権利への配慮を義務付け」、そして「重大な違反があった場合に解散命令の対象となることを明確にすること」を提言している。

もし宗教団体やその構成員も、ガイドラインで示された児童虐待にあたる行為を行ったり、親にそうした行為を促した場合、それは事実上、児童虐待を共同で行っていること、または助長していることになる。
さらに、宗教的または思想的な理由に基づいて子どもの権利を侵害する行為については、明確に定義するとともに、重大な侵害は刑事処分を受けるとしている。具体的には、児童虐待防止法や児童福祉法を改正し、「宗教活動や教義等に基づいてなされる子どもの福祉を侵害する行為を具体的に列挙して禁止すること」が明示されている。
宗教法人の解散を認める規定にある「公共の福祉に害する」という曖昧な表現に続き、今度は「宗教活動や教義等に基づいてなされる子どもの福祉を侵害する行為」という、新たな曖昧な概念が登場した。つまり、将来的に親や宗教法人の構成員に刑事罰を科すことを可能にする立法の導入が推奨されているのである。
この「福祉」という概念の曖昧さについては、国連人権委員会がこれまで繰り返し指摘しており、日本に対し、宗教または信条の自由を制限する目的でこの概念を用いることをやめるよう求めてきた(2008年、2014年、2022年の自由権規約人権委員会「総括所見」)。
以上の理由から、これらの国会への提案は却下されるべきである。

Patricia Duval is an attorney and a member of the Paris Bar. She has a Master in Public Law from La Sorbonne University, and specializes in international human rights law. She has defended the rights of minorities of religion or belief in domestic and international fora, and before international institutions such as the European Court of Human Rights, the Council of Europe, the Organization for Security and Co-operation in Europe, the European Union, and the United Nations. She has also published numerous scholarly articles on freedom of religion or belief.