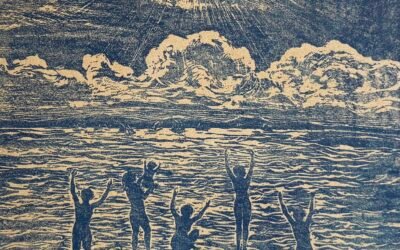パトリシア・デュバル
7本の記事の7本目(1本目・2本目・3本目・4本目・5本目・6本目の記事を読む)
Read the original article in English.

ディプログラミングは、統一教会を破壊するための武器として用いられ、日本の裁判官のサポートのもとで行われていた。反カルト弁護士たちが、統一教会信者に対する違法な監禁や強制脱会という違法行為に加担していたにもかかわらず、弁護士会からの懲戒処分は一切なく、むしろ日本の裁判所は、政府が宗教法人解散の根拠とした民事裁判において、こうした行為を容認してきた。
上記で紹介した札幌地裁での最初の「青春を返せ訴訟」において、裁判所によると、教会の「伝道活動」や自由意思の侵害などを訴えた原告20人のうち、少なくとも16人が、監禁され、強制的に脱会させられていた(おそらく20人全員がこのような扱いを受けていた)。
被告側弁護士が、彼らの証言は信頼性に欠けると主張したにもかかわらず、札幌地裁はこの主張に応えることなく、原告の主張を認め不法行為の成立を認定した。控訴審では、札幌高裁も前審の判断をおおむね維持したが、ディプログラミングについては具体的な見解を示した。
控訴審の判決にて拉致監禁について以下のように述べている:
「控訴人は、多くの被控訴人らが、身体の自由を拘束されるなどの手段によって棄教に至っていることが重大な問題であり、これを無視した判断は司法の公平・公正に反すると主張する。上記認定のとおり、被控訴人らはいずれも控訴人を脱会(棄教)した者であり、脱会に至るまでの過程において親族らによる身体の自由の拘束等を受けた者も多く、このような拘束等は、当該被控訴人らとの関係においてそれ自体が違法となる(正当行為として許容されない。)可能性がある。しかし、それは上記のような行為をした者と当該被控訴人らとの関係であって、必要に応じて別途処理されるべきことがらにすぎず、このような事情が存在することは控訴人の被控訴人らに対する責任に何ら消長を来すものではない(むしろ、その終期をもたらしたものといえる)。したがって、控訴人の責任を判断するに当たって控訴人の主張するような脱会までの経緯等を斟酌しなかったからといって、その判断が司法の公平・公正に反することになるものではなく、上記主張は失当である。」
要するに、原告たちが再度の監禁を恐れ、強要のもとに教会を訴えたという事実は、まったく考慮されなかったのである。

実際、同高裁は踏み込んで、「むしろ、その終期をもたらしたものといえる」とまで述べた。つまり、少なくともディプログラミングによって、教会による「洗脳」や原告らに対する不法行為は終了した、という意味である。
この問題を個人の問題として矮小化し、原告に対して加えられた暴力を無視し、それが本来「公共秩序の問題」として国が責任持つべき事柄であるという観点を、自発的に無視することで、裁判所はこの行為(ディプログラミング)を容認したのである。
政府が宗教法人解散請求の根拠とした32件の訴訟の大多数は、ディプログラミングを受けた元信者によって起こされたものである。これらすべての捏造された訴訟において、裁判所は原告の監禁や強制脱会の事実について認定しながらも、それに基づくいかなる結論も導き出さなかった。
これは、裁判官の中立義務や公正な裁判を受ける権利の侵害にとどまらず、日本が署名・批准している『市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)』、とりわけ第18条第2項に規定された「宗教または信念の自由」の侵害について、日本国の責任を問うものとなる。同条項には次のように明記されている:「2. 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」
この規定に基づき、国連自由権規約人権委員会は2013年の日本審査の際に、この問題を取り上げ、2014年8月20日の総括所見において以下の勧告を盛り込んだ:
「拉致及び強制改宗」 21.委員会は、新宗教運動の回心者を棄教させるための、彼らに対する家族による拉致および強制的な監禁についての報告を憂慮する(2条、9条、18条、26条)。締約国は、全ての人が自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない権利を保障するための、有効な手段を講ずるべきである。

数か月後の2014年11月14日、こうした不当行為の被害者である後藤徹氏が、東京高等裁判所において家族および2名のディプログラマーを相手取って提訴した民事訴訟で、初めて多額の損害賠償を勝ち取った。これは、彼の信仰を棄てさせるため、12年間にわたり違法な監禁および強制説得が行われたケースであった。裁判所はその被害に見合った賠償金の支払いを命じ、また、松永堡智牧師によるディプログラミング行為そのものが違法であると明確に認定した。この判決は、2015年に最高裁判所によって確定された。
しかし、その後「ディプログラミング」が表向きには終息したように見えても、このように今まで構築されてきた裁判が、今や統一教会の解散とその破壊を実現するために利用されており、まさに当初からの全国弁連の弁護士たちの計画通りである。彼らは違法行為に加担していながら、一度も責任を問われていない。
もし解散命令が控訴審でも支持されれば、統一教会が犯罪組織であるという非難や、信者たちが犯罪者であるかのように烙印を押される風潮が高まるだろう。その結果、このような野蛮な行為が再び横行しかねない。

Patricia Duval is an attorney and a member of the Paris Bar. She has a Master in Public Law from La Sorbonne University, and specializes in international human rights law. She has defended the rights of minorities of religion or belief in domestic and international fora, and before international institutions such as the European Court of Human Rights, the Council of Europe, the Organization for Security and Co-operation in Europe, the European Union, and the United Nations. She has also published numerous scholarly articles on freedom of religion or belief.