文化庁は、抗告審で解散決定が確定した場合、統一教会を清算するための徹底的な措置を継続すると明言している。
マッシモ・イントロビニエ

中国専門家である「Bitter Winter」の私たちは、この儀式に慣れきっている。政府機関が自由を制限する政策案を発表し、厳粛に「パブリックコメント」を募り、そしてまるでシュレッダーからウサギを引きずり出すマジシャンのように、否定的な意見は的外れか、誤解に基づいているか、あるいは組織的に行われた疑いがあると発表するのだ。いま、それが民主主義国家である日本で起こっている。実際、日本の文化庁は宗教法人の解散に関する指針案で、この皮肉な演出を新たな次元へと押し上げた。この指針案は、信教の自由を擁護するふりをしながら、旧統一教会の資産を剥奪するために作られたかのようだ。
2025年9月3日、文化庁は「指定宗教法人」の解散後の清算手続きに関する指針案を公表した。現在「指定」されている唯一の団体は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)である。なお、第一審の解散決定が抗告審で支持された場合、最高裁判所への上告の可能性はあるものの、清算手続きは直ちに開始される。
指針案には、将来の被害者を想定した「遅延申請」を含む、長期間にわたる請求手続き期間の規定、解散した宗教団体を代理する補償財団の設立、新たな「被害者」探しのために設置されたとみられる「相談窓口」や「説明会」、そして宗教的利用に関連する資産を含むすべての資産を処分する権限を与えられた清算人に関する規定が含まれている。指針案は「非宗教的な不動産から処分すべき」と規定しており、清算手続きを妨げないという前提付きで、宗教の自由を表面的に認めているに過ぎない。
要するに、被害者救済を装った資産差し押さえの青写真である。草案には、信者らが「清算を妨げない限り」施設の利用を継続できるとさえ示唆されている。それはまるで、ブルドーザーが到着するまで家に住み続けていいと告げるようなものだ。
しかし、ここで茶番劇はオーウェル風に展開する。2,649件ものパブリックコメント(その多くは宗教の自由の侵害に対する懸念を表明するものだった)が寄せられたにもかかわらず、文化庁はそれらを無視することに決めたのだ。なぜか? それは、それらのコメントが家庭連合のウェブサイトに掲載されている主張と「類似していた」からだ。つまり、標的となった宗教の信者であれば、あなたの意見は考慮されない。たとえ信者でなかったとしても、たまたまその主張に同意するなら、あなたの意見は考慮されない。これは公聴活動ではなく、イデオロギー的な「ゲートキーピング」(訳者注:フィルタリングや排除のこと)なのだ。
却下された懸念事項の中には、「信教の自由に配慮し、(清算法人の)宗教目的の財産は債務の弁済の原資とすべきではない」といった記述や、「法人の財産を清算人が管理・処分できるのは信教の自由に対する侵害だ」といった記述があった。
文化庁は、これらの点は検討会で「既に議論済み」であるため、草案を修正する必要はないと回答した。つまり、「ご意見ありがとうございます。それでは私たちがそれを無視するのを見守ってください。」ということだ。
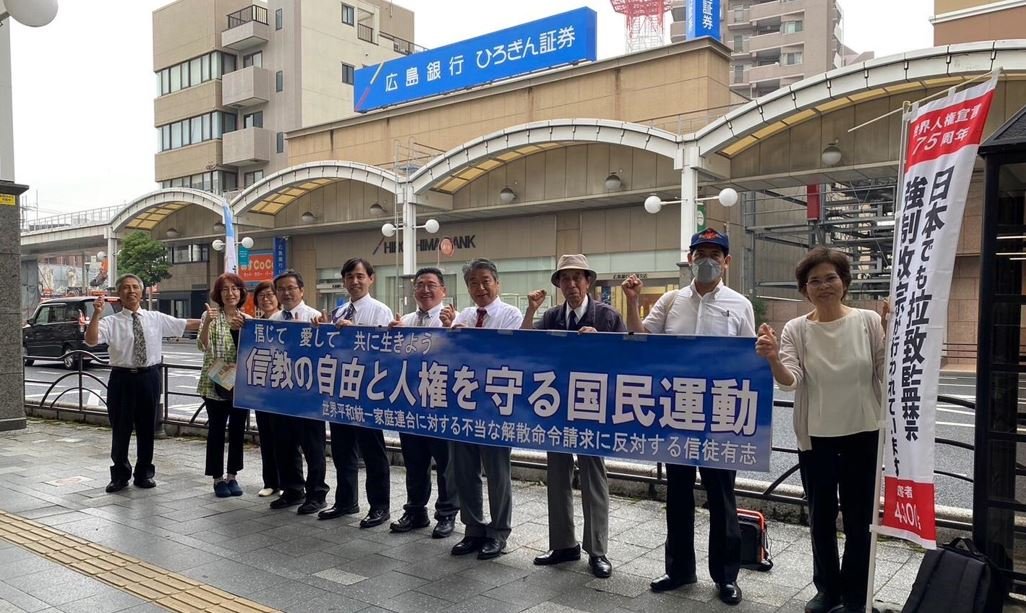
中国の立法府のやり方との類似性は驚くほどだ。中国でも法案は意見募集のために公開されるが、世論の反応に関わらず承認される。日本の文化庁は中国のやり方をそのまま真似しているようだ。意見を求め、反対意見を却下し、強引に進めるのだ。
国連は既に日本による統一教会への対応を非難している。国連特別報告者は痛烈な報告書の中で、「解散決定の根拠となった民事上の不法行為判決は、『公共の福祉』を著しく害するとされた『社会的相当性』の逸脱に依拠している。自由権規約人権委員会が既に指摘しているように、『公共の福祉』の概念は曖昧で無限定であり、市民的及び政治的権利に関する国際規約で許容される範囲を超える制限を許容する可能性がある」と警告した。
つまり、国連の声明は、統一教会の行動が「社会的相当性」を欠くとみなされるという理由で統一教会を解散させ、その資産を清算することは、宗教または信条の自由の権利の侵害に当たる可能性があることを示唆したのである。
被害者救済を装って清算の指針案を策定し、公募したコメントを「カルト」によるプロパガンダだとして却下し、宗教差別に関する国際的な警告を無視する政府機関もまた、宗教や信仰の自由と民主主義の基本原則を侵害している。もしこれが文化政策だとしたら、それは権威主義的な文化である。
日本の文化庁は「被害者」を守ると主張するかもしれないが、真の被害者は宗教または信条の自由である。そして、宗教の自由を擁護する人々は、政府が耳を傾けようとしない声の合唱団に貶められている。

Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.



