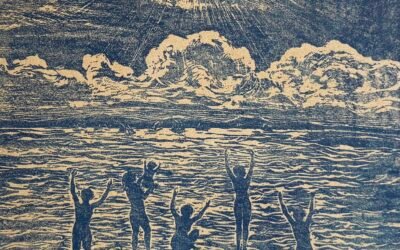統一教会を公然と批判する背教者よりも、喜んで信仰を守り続けている二世の方がはるかに多い。
マッシモ・イントロヴィニエ
Read the original article in English.

前回の記事では、カナダの研究者アダム・ライオンズが提示した、20世紀の最初の「カルト論争」と、2022年の安倍晋三元首相暗殺をきっかけに始まった新しい「カルト論争」との違いについて論じた。
その違いは大きく、ライオンズの研究は時宜を得た重要なものだといえる。しかし一方で、第一次と第二次のカルト論争には共通点がある。とりわけ、前者における一世の背教者の役割と、後者における二世の背教者の役割がそうである。
一世、二世を問わず、自らがかつて所属した宗教(あるいは二世の場合は親の信仰)を公然と非難する人々には、背教者の特徴として、ブロムリーらが第一次カルト論争の中で指摘した二つの要素が見られる。第一に、彼らは少数派であること。第二に、反カルト運動との接触を通じて背教者となることである。
第一に、二世の背教者は宗教を離れた人の中でも少数派である。さらなる実証研究は必要だが、一世の場合と同様に、二世においても背教者は普通の離教者に比べ少数派であることが示唆されている。親の宗教を離れ、静かに世俗社会へと溶け込んでいく二世の方が、背教者となる二世よりもはるかに多い。
さらなる数量的データが必要であるものの、ライオンズは自身が行ったソーシャルメディアやウェブフォーラム、インタビューを通じた調査に基づき、次のように結論づけている。「公共空間で拡散されている二世の不満や被害の物語は、日本の新宗教で育った人々のうち、統計的には少数派の意見にすぎない。それでも、こうしたストーリーの人気は、現代日本社会における規範的な世俗主義や組織宗教への反感を強める働きをしている。」
アメリカの研究者ホリー・フォークも次のように同意している。日本に限らず他国でも、「二世の中で最も多いのは“受動的な離脱者”であり、統一運動に積極的に関わることもなければ、公然と批判することもない人々である。」
多くの二世は信仰を離れることなく、親の信仰に喜んでとどまり、それを守っている。ジャーナリストの福田ますみ氏は、統一教会信者として現在も活動する23,486人が、解散に反対する嘆願書に実名と住所を添えて署名したことを報告した。これに対し、反カルト側は解散賛成を求めるオンライン署名を20万筆以上集めたが、そちらには本人確認の手続きがなかった。
解散請求の裁判に要望書を提出した者、インタビューに応えた者、国会で意見陳述した者、さらに氏名変更申し立てをした一人を合わせても、公に姿を現した二世の背教者は11人である。そのうち8人は、2025年7月24日に統一教会を相手取り損害賠償を求める、いわゆる集団訴訟を起こしている。公には出ていないものの、不満を抱える二世が多少は存在するかもしれない。しかし、そうしたケースを含めても、教会に喜んでとどまり信仰する二世や、特に批判することなく去っていった二世に比べれば、その数は依然としてごく少数である。

これら二世背教者の物語には、事実と異なるものがある。ライオンズが「統一教会二世の“顔”」と紹介している小川さゆり氏(仮名)の主張については、福田氏自身が反論しており、小川氏が両親に対して訴えた多くの内容は事実でないことが明らかになっている。ライオンズはまた、福田氏が小川氏を批判した記事が国際的に高く評価されていることを指摘している。特に、『Bitter Winter』に掲載された英語版記事や、『The Journal of CESNUR』に掲載された注釈付き記事がそれである。ところがライオンズによれば、「日本国内では主要紙、日本の研究者、さらには日本語版ウィキペディアにおいても」福田氏の記事は引用されていない。
私たちがイタリアで福田氏の記事をファクトチェックした際、彼女からは銀行明細や写真など数十点に及ぶ資料が提供された。小川氏に関する議論において、日本で福田氏の名前が引用されないのは、ジャーナリストとして調査に不備があるからでなく、日本のメディアや学界に根強い「背教者寄りの偏向」があるからである。
小川氏の事例は、一世と二世の背教者に共通する第二の特徴を表している。つまり、彼らは自分の意思だけで背教者になるのではなく、新宗教に反対するサブカルチャーに取り込まれ、反カルト団体や専門家の影響を受けているのである。そして、このコミュニティは背教者をしばしば「公の顔」として利用する。
日本における事例の特徴として、ディプログラミング(脱会説得)を受けた後、多くの元信者や二世が統一教会を相手取って訴訟を起こすケースがある。彼ら(ディプログラミングの被害者)は、監禁が続くことを避けるため、法的措置を取らざるを得なかった。
「伝統的」な一世の背教者と同様、統一教会やエホバの証人などの宗教を強く批判する二世は、信仰を棄てても公に批判したりメディアに語ったりしない大多数の元信者や二世の集団に比較すれば、ごく少数にすぎない。さらに親の信仰に喜んでとどまっている二世に比べても、はるかに少ない。
しかし、メディアに映るのは背教者となった二世ばかりであるため、多くの報道はあたかも「背教者」を、元信者や全ての二世を代表する存在のように扱うという誤りに陥っている。これはよくある誤解であり、宗教の自由に深刻な悪影響を及ぼす。

背教者の証言を軽視すべきではない。しかし、中立性と客観性を確保するためには「三角測量」の手法が必要となる。つまり、背教者の証言を、運動にとどまっている現役信者、背教者にならなかった元信者、さらに内部資料を研究し、インタビューや資料調査、参与観察を行った学者の記録と照らし合わせる必要がある。加えて、この三角測量を真に適用するなら、告発された宗教団体にも、背教者の主張を検討し、反論する機会が与えられるべきである。
こうした多様な情報源を多角的に検証してこそ、質の高いジャーナリズムが生まれる。一方、背教者の証言だけに依拠する報道は、偏った物語をつくり出し、差別の道具となってしまう。

Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.