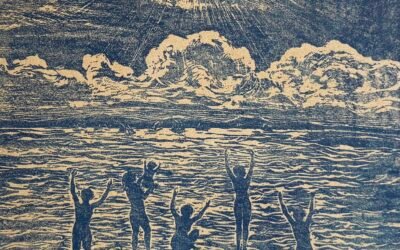その手続きは、日本国憲法及び国際社会における義務に反するものであり、「法令違憲」と「適用違憲」のいずれか、あるいは両方に基づいており、公正な裁判のルールに違反して行われている。
小林節
5本の記事の5本目。1本目と2本目と3本目と4本目を参照のこと。 日本語原文の括弧内の参照はそのまま残した。
Read the original article in English.

総括
地球上の生物の中で宗教を持っているのは人類だけである。
古来、宗教は国家権力を超えた主体への帰依をその本質とするために、国家権力との対立を招くことが多く、その故に、信教の自由は「あらゆる人権の先駆け」になったと言われてきた。
当人の人格の本質と尊厳に関わる宗教活動は、「その故に犯罪を行わない限り公権力による介入は許されない」という憲法原則が、自由民主主義諸国では確立されている。
今回、不可解な安倍晋三元首相の暗殺事件をきっかけに高まった「反・統一教会」という世論に押されるように、岸田首相(当時)は同教会の解散命令を裁判所に請求し、東京地裁は本年3月25日に解散命令を決定した。教会は現在、東京高等裁判所に抗告中である。
それにしても、この過程で、国家による多くの違憲な決定が重ねられてきた。
まず、自由民主主義諸国で等しく確立されている憲法理論として、信教の自由はいわゆる「優越的人権」で、それを国家が規制せざるを得ない場合には、「重大な公益に対する侵害(要するに「犯罪」)を行ったという事実」があり、その害悪を除去するために「最も弾圧的でない手段」しか行使してはならない…という「厳格違憲審査」の原則がある。
この点で、旧統一教会は、無差別殺人を実行して解散を命じられたオウム真理教とは異なり犯罪は行っておらず、献金を巡るトラブルで、かつて32件の民事訴訟で敗訴して既に責任を取っている。それに加えて、プロの脱会指導業者の下で訴えてきた元信者の心の平和を考えて返金した事例まで合わせて、『法令に違反して著しく公共の福祉を害した』と認定されて解散を命じられてしまった。しかし、これは明らかに「過剰(overbroad)な規制」である。和解に応じて解決済みの事実についてまでさらに法的責任を取らされるとは、一体どういう理論的根拠があるのか?が示されていない。
宗教法人法81条1項には、「『法令』に違反して著しく公共の福祉を害した」場合には解散を命じることができる…と書かれているが、これでは、条文上、「違法」になる行為の概念が広すぎてまるで国家が作った「落とし穴」のようで、典型的な「過度に広範な規制」である。これは条文自体が違憲ないわゆる「法令違憲」である。
さらに、この条文の『法令』という文言を『刑法』と狭く読む解釈・運用もできるはずであるが、あえてそれをしなかった岸田内閣による「有権解釈の変更」とそれに従った司法府の決定は、明らかにいわゆる「適用違憲」である。

加えて、この宗教法人の解散を決定する手続きには、構造上の重大な欠陥がある。
宗教法人法81条7項は、この手続きは「非訟事件手続法」で行うと規定している。これは、要するに、宗教法人の解散命令は、離婚に伴う婚姻費用の分担の決定等のように、国家による「後見的監督」(つまり、後ろ盾になり『保護』する行政作用)により紛争を予防・解消する手続きが相応しい…という立法政策によるものである。
しかし、今回の宗教法人解散命令の決定過程は、その本質において「後見」などというものではない。つまり、各自の良心に従い、犯罪も行わずに信仰生活を続けてきた旧統一教会の会員にとっては、自分たちの人生の基盤そのものである教会が、今回、国家により「取り潰される」に等しい状況に追い込まれている。その結果、解散になれば、信徒たちは、社会的なレッテルを貼られ、教会の財産(礼拝堂や活動資金等)は国家が任命した清算人の管理下に入ることになる。つまり、信者たちの生活の土台が国家の管理下で解体される手続きが今、進行しているのである。
この関係は、非訟事件手続の本質である国家による「後見的監督」などではない。まさに、教会と信者にとっては、己の良心の故に国家から「疑われ」「追いつめられ」「生き方の変更までを強いられている」わけで、この状況は、「国家からいわば『襲われた』国民による国家を相手にした人権闘争」そのもので、法的紛争(典型的な『法律上の争訟』つまり「訴訟」)である。だから、これは「非訟事件」などではない。
そうであるならば、教会側としては、憲法32条が全ての人に保障している「公正な裁判を受ける権利」を正当に行使すべき時である。それはまず、32条の総則である31条が保障する「法定適正手続」が保障されたものでなければならない。つまり、予め法律で定められた「正当な理由」と「公正な手続」なしに人権は奪われない…という保障である。
さらに、その「公正な裁判」とは、憲法76条3項で独立性が保障された裁判官による、憲法82条が保障する『公開』法廷における『対審』のことである。
現に、今回の非公開手続きの具体的な弊害として、解散命令を求める国側(文科省)から旧統一教会の悪質性を立証する証拠として提出された複数の陳述書が捏造されたという抗議が、教会側弁護士から出ている。それは、非公開の法廷における反対尋問で明らかにされた事実であるが、そのような重大な事実も、非公開で主権者国民による監視が届かない密室内で、無視されたまま、国家による教団解体の手続きが進んでいる。
このような違憲な手続きによる国家権力の行使は、日本国憲法の下では、旧統一教会に限らず、「だれに対してであれ」許されてはならないはずである。

結び
以上、改めて指摘しておくが、今、日本国の法廷で進行している旧統一教会解散命令の確定に向けた一連の法手続きは、次の違憲性を帯びている。
つまり、信教の自由という優越的人権(憲法20条)に対する制約として、事前に法定された「高度な正当理由」と「適正な手続き」がなく、それは、憲法31条(法定適正手続きの保障)、32条(公正な裁判の保障)、82条(公開・対審の保障)に違反しており、さらに、国際人権B規約18条1項(宗教の自由)および14条1項(公正な裁判を受ける権利)すなわち憲法92条2項(条約順守義務)にも違反している。
従って、この一連の手続きは違憲で、無効である(憲法81条[違憲審査権]、98条1項[最高法規])。

Setsu Kobayashi is a professor emeritus at Keio University and a lawyer. He is a Doctor of Law and a Honorary Doctor of Otgontenger University, in Ulaanbaatar, Mongolia. Born in Tokyo in 1949, he completed his doctoral course at Keio University Graduate School of Law in 1977. After working as a visiting scholar at Harvard Law School, he was a professor at Keio University from 1989 to 2014. During that time, he also served as an invited professor at Peking University and an associate fellow at Harvard University’s Kennedy School of Government. In 2014, he became a professor emeritus at Keio University. His books include “Constitutional Revision and Deterioration” (Jiji Press), “The Truth of Constitutional Revision” (co-authored with Yoichi Higuchi, Shueisha), “Politicians Who Do Not Understand ‘Human Rights’” (Kodansha), and several others.