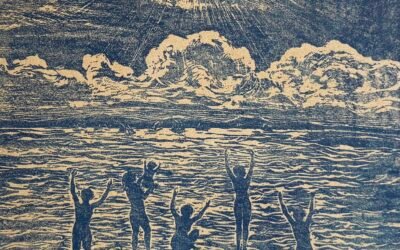背教者となった元信徒は、反カルト運動から自らの役割を「学ぶ」ことが多い。
マッシモ・イントロヴィニエ
Read the original article in English.

前回の記事では、元信者と背教者という2つの異なる概念を混同すべきではないことを確認した。ほとんどの元信者は、離れた組織に対して攻撃的な感情を持っていない。過激な敵対者となるのはごくわずかだ。しかし、なぜなのか? 背教者になる人にはどのような目立った特徴があるのだろうか。
学者たちが考慮した要因は2つある。1つ目は宗教組織に関することで、2つ目は離脱のプロセスに関することだ。通常、物議を醸す宗教団体であるほど、背教者の数が増えるだろうとみなされている。ブロムリーは、どの宗教にも背教者は存在するが、そのほとんどは反対派が「破壊的」であるというレッテル貼りに成功したグループの元信者の中にいると主張した。逆に、非常に尊敬されている組織はより多くの離脱者を生み出すが、背教者は少ない。
その比較は、その人が生まれながらに所属する教派間、教会間ではなく、個人が自由に加入する志願制の団体間で行うことが好ましい。しかし、主流派の教会の中にも修道会や信徒運動など、いくつかの志願制の団体が存在するし、ローマ・カトリック教会の司祭職でさえも一般的にはそうなのである。カトリックの司祭や修道女を辞めた人々の中には極めて声高に発言する背教者もいるが、司祭職や修道会を辞めた人々の多くは、むしろ教会の基準を満たしていない自分を責める傾向にある。したがって、彼らはしばしばタイプ I (脱落者) の物語を用いて自分の経験を再構築する。ブロムリーらによれば、こうしたことが起こるのは、ローマ・カトリック教会が強力な(もちろん、挑戦不可能というわけではないが)組織であるからだという。したがって、大抵の場合は、離脱しようとするメンバーとの間で物語のダメージコントロール交渉をすることが可能なのである。それとは対照的に、ほとんどの新宗教運動を含め、破壊的であると認識されている組織は通常、離脱しようとするメンバーとの間で物語のダメージコントロール交渉をすることができず、結果としてより多くの背教者を生み出すのである。
この理論的な予想は、表面的には非常に合理的であるように見えるが、実証的研究によって完全に確認されているわけではない。新宗教運動は通常、破壊的であると認識されており、非常に声高な背教者を生み出す傾向にある。しかし、これまで見てきたように、可能な限りの調査が示唆しているのは、最も物議を醸している新宗教運動であったとしても、背教者は元信者の中でもごく一部の少数派を代弁しているに過ぎないだろうということだ。元信者の大多数は普通の離教者に分類でき、中には脱落者もいる。
ここで、目立つ元信者と目立たない元信者の区別が確立されるであろう。ほとんどの元信者は、以前の所属について物議を醸す気がない限り人目に付くことはない。実際、多くの場合その存在自体が、団体の会員記録にアクセス可能な定量的調査によってのみ発見が可能なのである。それらが質的な社会学的研究のために入手される可能性はさらに低い。目立つ元信者は主に背教者であり、彼らが反対派連合に加入すると、反対派連合は彼らの知名度を確保するためにあらゆる努力を傾ける。
実際、脱会のプロセスには決定的要素が関わっている。拉致されて成功裏に「ディプログラム」された者たち、すなわち「カルト」を離脱するよう激しい心理的圧力を受けた者たちは、背教者になる可能性がはるかに高いことを全ての研究が示している。「ディプログラム」の成功によって脱会した者たちは、「カルト」とレッテルを貼られた運動からの脱会者らの中では少数派であるが、それは背教者も同様である。
ディプログラムによるのでなかったとしても、宗教団体を離脱する人の一部は、脱会前、脱会中、脱会後に反カルト運動に遭遇する。なぜなら、反カルト組織と接触した親族によって脱会プロセスが開始するからである。あるいは脱会を検討している人は、自分の属する宗教に対する批判に好奇心を持っていたり、純粋に興味を持っているからである。
私は前回の記事で、フランスのニュー・アクロポリスと呼ばれる秘教グループの元メンバーについて自身が行った定量的研究について述べた。 私のサンプルの8.3% は、反カルト組織との接触が自身の脱会プロセスにおいて役割を果たしたと報告した。 背教者の70%は反カルト組織と接触していた。そのような接触を持つ人々の90%は、ニュー・アクロポリスを「カルト」だと考えているのに対し、その他の人々は10.3%であり、80%が自分は「洗脳」されていたと信じているのに対し、その他の人々は6.7%だった。もちろん、一部の元信者にとって背教は心理的に好都合である。その理由は、元信者から見れば、今となっては間違っていたり愚かにさえ思える行動や信念に対していかなる非難を受けても、彼らを「洗脳」あるいは「奴隷化」した「邪悪な」運動に責任転嫁できるからである。

反カルト運動が背教者を生み出す上で中心的な役割を果たしているとすれば、ブロムリーが書いたように、今度は「背教者の証言が、反カルト運動が主催するあらゆる範囲の社会統制活動の中心となる。」その目的は、新宗教運動を差別し、可能であれば抑圧することにある。背教者の一部には、(統一教会からの背教者であるスティーヴン・ハッサンのように)ディプログラマーとなり、専門的および学術的な資格を取得した者さえいた。その他多くの者たちは反カルト運動との接触を維持し、ブロムリーの言葉を借りれば、自分たちが離脱した組織の「道徳的地位の低下」のために活動を続け、その結果「その団体に満足している信徒は洗脳されているのだと片づけられ、市民プロジェクトは人目を引くためのPR活動とみなされ、組織の関連団体は『フロント団体』とレッテル貼りをされてあざけられ」、背教者の説明を疑う学者には「カルト擁護者」というレッテルを貼ってあざけるようになるのである。
ブロムリーはまた、さまざまな種類の「背教者の職業」についても説明している。元の宗教に反対する本や講演で生計を立てたり、収入のかなりの部分を得ている者もいる。他の元信者を勧誘して背教者に変えようとする者もいる。そして、反カルト運動は背教者を利用して、彼らが「カルト」とレッテルを貼る宗教に対する攻撃の中で、「申し立てのあった違反行為は非常に根本的かつ大規模なものであり、(カルト側の)無実を訴える抗議などは即座に拒否されるほどだ」と主張する。背教者の物語を広めることによって「(カルトに)敵対的な世論の風潮が作り出される」と、「調査公聴会」や裁判、政府による差別を通じて「社会統制」と公的「制裁」が発動される。(ブロムリー著「争われた退会者の役割の社会的構造」42-3)
結論として、背教者は新宗教運動の元信者の中では比較的小規模な少数派でありながら、最も目立つ存在である。それは反カルト運動に動員されるのは彼らだけであり、メディアが利用しやすく、元の組織に対する訴訟で証言する準備ができているからである。
このシリーズに目を通してきた者なら、それが2つの結論に至ることはお分かりであろう。1つは、背教者は大多数の元信者の代表ではないということ、もう1つは背教者の物語は、反カルト運動及びそのイデオロギーとの出会いによって決定的に形成されるということである。
もちろん、背教者がする報告がすべて虚偽だということではない。実際、背教者の説明がすべて嘘だという新宗教運動の研究者はいないであろう。また反対派が広めた風刺画とは対照的に、反カルト運動に批判的な学者たちは、背教者の文献を無視することはないであろう。それどころか、彼らはそれを収集し、かなり詳細で完全な参考文献のリストを出版することがよくある。彼らはまた、背教者が学者のさらなる研究に役立つ質問を組み立てるのを手伝ったり、場合によっては当局が確認できる実際の違法行為について注意を喚起する内部告発者として機能したりする可能性があることを認めているのである。
他のケースでは、虚偽の告発が法執行機関を誤導し、不必要な苦しみを生み出した。 例えば、ロシアと中央アジアでは、宗教というよりも微生物学(同氏はこの分野でも非常に物議を醸している)を専門とする学者ジェリー・バーグマンが作成したエホバの証人を非難する長々としたリストによって、国際機関やNGOが同教団に対するあからさまな迫害であると広く評してきたことが支持されてきた。バーグマンは1999年に初期のエホバの証人に関する有用な文献リストを編纂したが、中立的な学者としてではなく、エホバの証人を離れた怒れる元信者として書いている。ロシア語に翻訳され、インターネットで容易に入手できる彼の非難は、かつてソ連の一部であった国々の信教の自由と人権の大義を著しく侵害した。

メディアと法廷は以下のことを心に留めておくとよいであろう。背教者は新宗教運動の元信者という、より大きな領域を代表するものではなく、その中にあって背教者は少数派なのである。また当然のことながら、彼らは新宗教運動の中での生活についての唯一の証人でも、最も信頼できる証人でもない。確かに、彼らはそこにいた。しかし背教者にならなかった多くの会員や元信者もそこにいたのである。背教者は反カルト共同体の一員としてそのイデオロギーを共有し、元の宗教運動に対して過激な反対をする者と定義されるのだが、それ自体が歪みと偏見の強力な要因なのである。背教者たちが報告していることが新宗教運動に関する「真実」であると認めることは、怒れる元配偶者の証言に基づいて離婚した夫(ないし妻)の道徳的性格を評価したり、不満を抱いた元司祭たちの証言にのみ基づいてカトリック教会とは何なのかについて評価したりするのに似ているであろう。
背教者の説明は無視されるべきではない。しかし、中立性と客観性は三角測量法を前提としている。そこでは背教者の報告が、現役信者や背教者にならなかった元信者による説明と比較され、また、関連内部文献や記録文書の研究、インタビュー、及び参与観察を行った学者の報告と比較されるのである。真に三角測量法を用いるということは、告発されたグループが背教者の告発を調査し、それに反論することが許されなければならないということを意味する。これらすべての情報源を三角測量して考慮したメディア報道は、質の高いジャーナリズムを生み出す。唯一またはほとんどの情報源として背教者に依存するメディア報道は、誹謗中傷と差別の道具を生み出す。

Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.